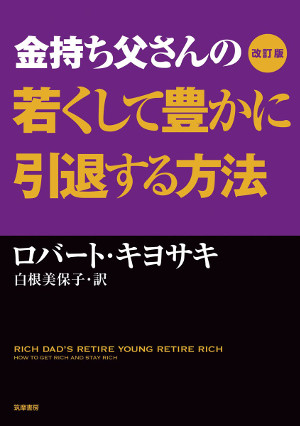史上最高値の43000円台へ
8月13日、マスメディアは揃って、日経平均株価が前日の12日に続いて取引時間中の史上最高値を更新し、初めて43000円台をつけたと報じた。
これは、前日夜にアメリカで発表されたCPI=消費者物価指数が市場予想に近かったことでFRBが想定通り早期の利下げに踏み切るのではとの見方が強まり、NY市場でS&P500などの指数が最高値をつけたために日本市場でも買い注文が多く入ったからだと見られている。
この間、先行き不透明感の原因となっていた関税問題が一段落したことも、市況が盛り上がっている理由のひとつだと考えていいだろう。
ただ、証券アナリストたちも、この相場が経済実態を伴っているかどうかが今後当然ながら問われることになり、いずれ反動がくるのではないかと見ているようだ。
すこし醒めた目で見れば、株価が上がっているのも金(ゴールド)の価格や不動産価格が上がっているのも、実は円の価値が下がっているということではないか、と思えてくる。
減税は実現するのか
実際、国内の景気を眺めてみると、果たして手放しで喜んでいいような経済状態だろうかと疑問が湧いてくる。
7月上旬には、6月までの半年間に全国で倒産した企業の件数が12年ぶりに5000件を超え、その要因として物価高や人手不足などがあるとみられる、との報道があった。
テレビのCMを眺めていると、中古品の買い取りや隙間バイトのサイトなど、どうやってお金を得るか悩んでいる層をターゲットにしたものが増えているようだ。
つまりは格差がさらに広がっているということだろう。
7月の参院選挙の結果を見ても、有権者の多くが消費税減税を訴えた政党に多く投票しているのは、重税感があり生活に余裕がない層が増えているからだと感じられる。
しかし選挙後の臨時国会では、すぐに行われるはずだったガソリン暫定税率の減税も先延ばしとなり、実現が危うくなっているようだ。
減税を訴えた政党は、しっかりとその実現に尽力してほしいものだと思う。
結局は米の生産不足
さて、選挙前にあれだけ話題になっていた米不足だが、いつの間にかほとんど取り上げられなくなったように思う。
8月5日、石破政権は「米の安定供給等実現関係閣僚会議」を開催し、今回の価格高騰の要因と対応の分析について議論し、生産量に不足があったことを認めた。
つまりは、流通の問題ではなく米の生産高がが足りなかったという実態を把握するのが遅れて対応が後手後手に回ったわけで、いまだに形を変えて続いていると指摘される減反政策など政府の農政の失敗を反省し、ここから大きく方向転換することができるのかが注目される。
今年の米については、この夏の水不足と大雨で作柄が心配だが、どうか無事に収穫の秋を迎えられるよう祈りたい。