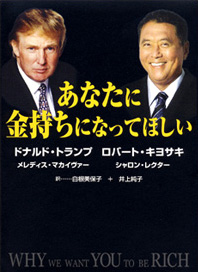ウォーレン・バフェットついに引退
GWが終わり、世間は普段通りの生活リズムが戻ってきた。
どれだけ休みが取れたかは人それぞれだと思うが、このさわやかな新緑の季節をみなさんはどんなふうに過ごしただろうか?
さて、連休の後半、ウォーレン・バフェットが94歳でついに引退するというニュースが流れてきた。
「投資の神様」と言われ投資会社バークシャー・ハサウェイを55年間率いて巨万の富を築いた彼が、どの株に投資してきたのか、その変遷を見ると興味深いものがある。
特に2000年以降は、最大の投資先だったコカ・コーラ株の割合がだんだん減っていき、2017年にアップルが保有株の首位に躍り出て2023年には保有額の半分を占めるようになった。
根強い需要がどこにあるのかをバフェットは常に見通していたわけだが、この先の動向を自分なりに予測して、彼ならいったいどの株に投資するのかと考えてみるのも頭の体操になるだろう。
非関税障壁としての消費税
「トランプ関税にどう対処するか」というのが最近の大きなテーマとなっているが、日本にはいったいどのような手立てがあるのだろうか。
日本が保有する米国債を取引材料にしてはどうか、という声も上がっているようだが、はたしてこれを有効に使って交渉する力量が今の政府にあるだろうか。
これまで、アメリカが関税問題を出してくるたびに、日本政府は農産物の輸入自由化を進めて輸入枠を広げ、自動車をはじめとする工業製品の輸出を守ってきた。
その結果、農業や酪農は守られないまま、政府は減反を進め、牛乳の廃棄や乳牛の殺処分を求め、日本の第一次産業は追い詰められることになって今の惨状がある。
だが、今回トランプ大統領が指摘してきたのは、非関税障壁としての消費税だ。
消費税引き下げを交渉の切り札に
以前にも取り上げたが、消費税の本質は実は輸出企業優遇税制であることはその仕組みを見ればわかる。
例えば、今年3月14日の財務金融委員会で財務省官僚が答弁したように、2023年度の消費税収23兆円あまりのうち8.8兆円はトヨタ自動車など輸出大企業20社に対する消費税還付金として使われた。
つまりこれが輸出奨励金のような役割を果たしているのではないか、というのがトランプ大統領が指摘している問題だ。
また、これまで消費税収は全額福祉に使われると政府が言ってきたが、実は消費税増税は法人税減税とセットで進められてきたことは自明である。
それならば、農産物を差し出すのではなく、消費税の引き下げ(あるいは廃止)を今回アメリカとの交渉材料にするのが一番の得策であり、また有効なのではないかと思うのだが、どうだろうか。